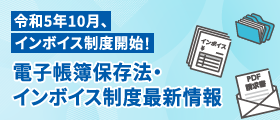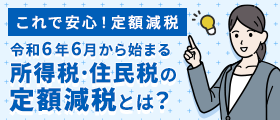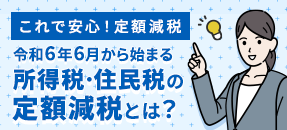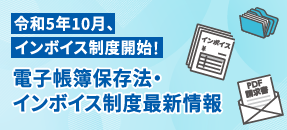60th ANNIVERSARY
当事務所は2023年に開業60周年を迎えました。
これも日頃からの皆様のご支援のおかげです。
改めて心より感謝申し上げます。
この先もさらなる発展を遂げ、100周年に向けて邁進してまいります。
今後もどうぞよろしくお願いいたします。




お知らせ
- 2024年4月5日 !緊急告知!
「待ったなし!定額減税への対応」セミナーを開催します。
- 2023年10月6日
コロナ後の経営戦略セミナーを開催しました。
- 2023年10月3日
資産防衛策セミナーを開催しました。
- 2023年10月2日
永年勤続表彰を行いました。
- 2023年9月11日
ホームページをリニューアルしました。
- 2023年9月1日
資産防衛・経営戦略セミナーを開催します。
- 2023年8月18日
普通救命講習を受講しました。
職員ブログ ~それぞれの小径(こみち)~
- 2024年4月12日
綺麗に、丁寧に、正確に
- 2024年4月5日
ありがとうの数だけ人は優しくなれる
- 2024年3月29日 教える立場と教わる立場
| 事務所名 | 税理士法人土田会計事務所 |
|---|---|
| 代表社員 |
税理士 土田 士朗(登録番号第82178号) |
| 住所 | 〒189-0013 東京都東村山市栄町1-36-84 |
| 電話番号 | 042-391-2269 |
| FAX番号 | 042-394-2335 |
| 税理士法人番号 | 1942 |
| 法人番号 | 2012705001526 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2012705001526 |
ここに見出しを入力してください
ここに見出しを入力してください
ここに見出しを入力してください